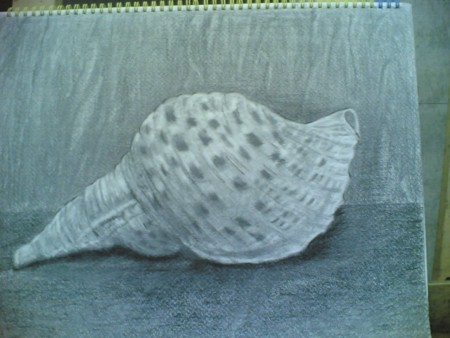An American style bar, a beer hall in the back, a variety of national languages flutter, interiors, customers and bartenders all blend together to create a world, and noblemen, businessmen, bohemian painters etc. are like friends without introducing each other. They call on the oldest bartender, "Hey, Bob" to confirm that they are part of this world.
Germans, Norwegians, Americans, they speak at least three languages.
While there are groups that dress up luxuriously and talk loudly and replace the aperitif that costs 10 francs a number of times, while dressing as hard as possible and trying to push themselves into the glitter here are just for that There are groups coming from all over the world, who sip an aperitif a few francs a cup.
In that hustle and bustle, there is a young red-haired Czech immigrant at the counter at the back of the bar, perhaps scooping a single spoonful of yogurt, the only meal of the day, from morning to night. The man's name is Radick, and no one approaches him.
The above is a scene from La Coupole, written by Georges Simnon in the Maigret Police Series "La Tete dun homme".
I've always been fascinated by this scene and on this occasion, with my friends, went to Montparnasse and stood in front of the La Coupole store.
I wanted to empathize with the Czech immigrant Radick in that situation and take his place. Why did he have to challenge a prominent Maigret police and commit a crime in order to satisfy his desire for approval?
However, the inside of the store, which was visible through the glass window, was dim and seemed difficult to access, so I decided to leave after a while hesitating.
Later, we strolled around the unexpectedly Americanized neighborhood of Montparnasse and sat down in a bright café where young people were enjoying conversation.
And I was interested in the difference between Saint-Germain-des-Prés, both of which are on the left bank of the Seine but still maintaining Paris, and Montparnasse, which was Americanized.
However, a quarter of a century later, I regret why I did not enter La Coupole at that time. I just had to push the door open.
The novel has the impact of placing the reader in the scene and wanting to remember the emotions of the characters.

アメリカ式のバー、奥にビアホール、様々な国語が飛び交い、インテリアも客もバーテンダーもすべての物が溶け合って一つの世界をつくり、貴人・ビジネスマン・ボヘミアン絵描きなどが互いに紹介なしに仲間内のようにはなしかけ合い、彼らは最古参のバーテンに「ねー、ボブ」と呼びかける事でこの世界の一員であることを確認しあう。
ドイツ人あり、ノルウェー人あり、アメリカ人あり、かれらは少なくとも3カ国語を操る。
贅沢に着飾って声高にしゃべり合い1杯10フランもするアペリティフを何倍もお代わりするグループがある一方で、精一杯着飾ってなんとかここのきらびやかさに自分を押し込もうと、たったそれだけのために世界のあちこちからやってくる一団がおり、彼らは1杯数フランするアペリティフをちびり、ちびり啜る。
そんな喧噪の中で、バーの一番奥のカウンターで、多分毎日の唯一の食事であるヨーグルトを一匙ずつ掬って朝から夜まで過ごす赤毛のチェコ移民の若い男がいる。男の名前はラディック、そして誰も彼には近づかない。
上記はジョルジュ・シムノンがメグレ警視シリーズ「男の首(日本語タイトル)」(La Tete dun homme))で描いた「ラ・クーポール」( La Coupole)の一場面である。
かねてからこの場面に惹かれていた私はこの機会にと友人と共に、モンパルナス(Montparnasse)まで足を運び、「ラ・クーポール」( La Coupole)の店の前に立った。
私はあの場面の、チェコ移民のラディックに感情移入して彼の立場に立ってみたかったのだ。なぜ、彼は、自分の承認欲求を満たすために著名なメグレ警視に挑戦して犯罪を起こさなければならなかったのか。
しかし、ガラスの窓を通して見えた店内は薄暗く、いかにも入り難くそうだったので、私はしばらく逡巡したものの立ち去ることにした。
その後、私たちは予想外にアメリカナイズされたモンパルナス界隈を散策し、若い人たちが会話を楽しんでいる明るいカフェに腰を下ろした。
そして、私は、共にセーヌ川左岸でありながら、パリそのものを維持しているサンジェルマン・デプレと、アメリカナイズしたモンパルナスの違いに興味を抱いた。
しかし、四半世紀を経た今でも、何故あの時私はラ・クーポールに入らなかったのかと後悔している。ドアを押し開けさえすれば良かったのだ。
小説には読者をその場面に身を置かせて登場人物の感情を偲びたくさせるインパクトがある。